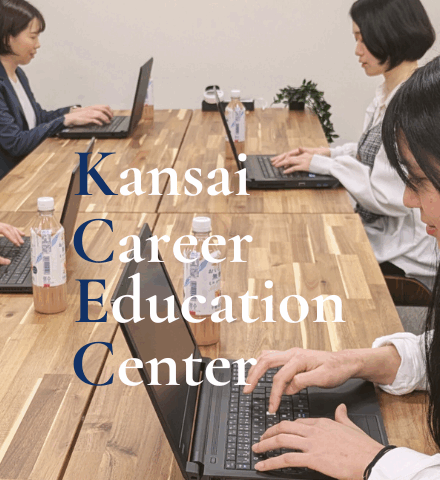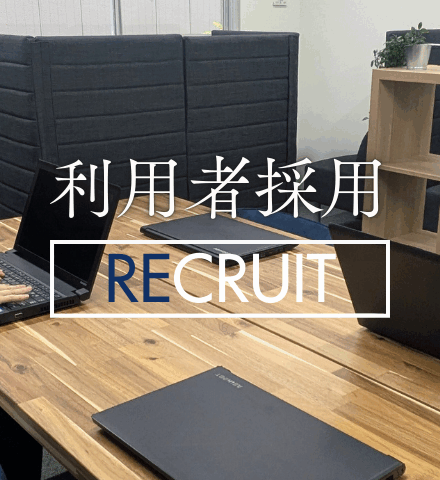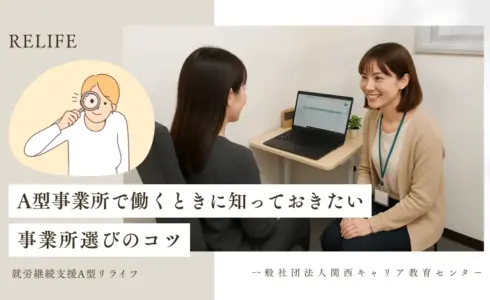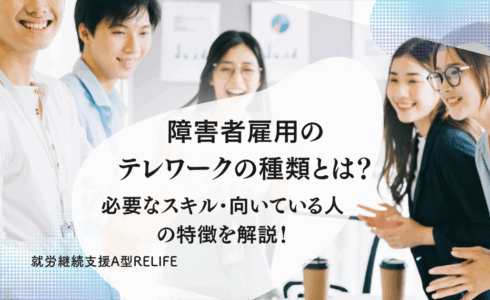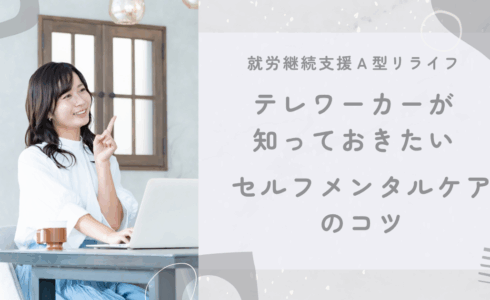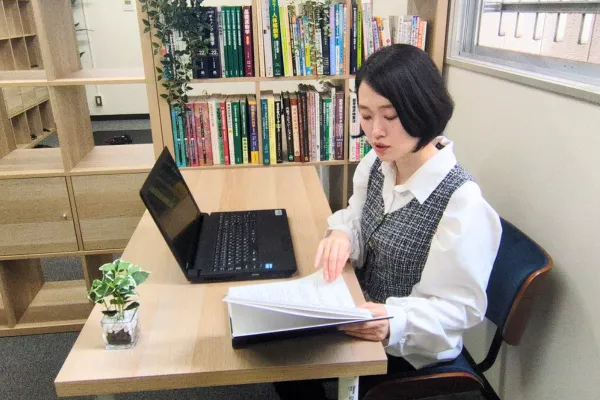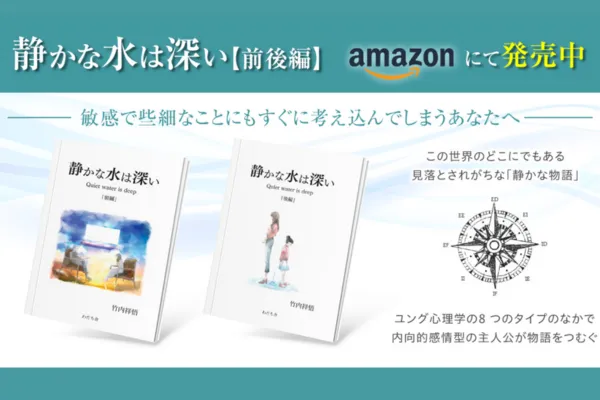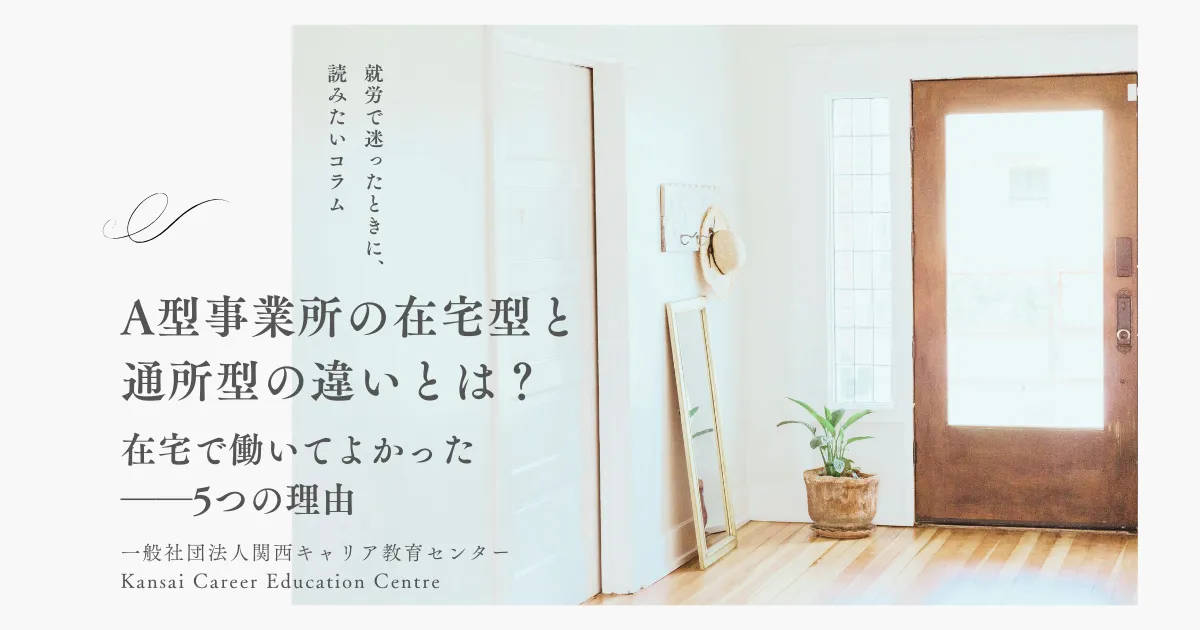
A型事業所の在宅型と通所型の違いとは? 在宅で働いてよかった5つの理由
皆さんは、就労継続支援A型には「在宅型」があることをご存じでしょうか?
A型事業所は、障がい者の方に就労の機会を提供する福祉施設です。
従来の通所型のA型事業所では、施設のある現地に通いながら就業する、という形が一般的でしたが、
 利用検討中のAさん
利用検討中のAさん

利用検討中のBさん
と感じたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

2020年以降は「テレワーク」が広まり、
A型事業所でも「在宅勤務」ができる施設が増えてきました。
今回は、
・「在宅型」に通ってよかったメリット
をご紹介します。
いま「在宅型のA型事業所」で働くかどうか、迷われている方の参考となれば幸いです。
「在宅型」と「通所型」の
働き方の違い

A型事業所の「在宅型」と「通所型」の主な働き方の違いは、
② コミュニケーションが直接的か、間接的か
③ チームでの作業か、個人での作業か
④ テレワークか、軽作業か
この4つです。
① オフィスで働くか、自宅で働くか

「通所型」と「在宅型」の最も大きな違いは、ご利用者の「就業場所」です。
一般的な「通所型」のA型事業所では、作業所のある現地やオフィスに利用者が通いながら勤務します。
A型事業所では、平日の「週5日」勤務がメインとなるため、オフィスへの通勤がひとつのハードルになります。
一般就労に向けての訓練として「通勤に慣れること」も必要になるので、
毎日の自宅と事業所の往復を「負担」と捉えるのか、「就労に役立つ」と考えるかで、働き方が変わってきます。

一方で、身体障がいがあり、就業する時に「通勤が占める負担の割合」が明らかに大きく、
能力・スキルがあっても「通勤」が難しいときは、「在宅勤務」がおすすめです。
また、精神障がいの方の場合、身体的な歩行動作には問題がなくとも、
・電車内などの閉じられた空間が苦手
・街中で人目が気になってしまう
といった障がいによる症状に悩まされてしまうこともあります。
そういったときに「在宅型」の就労支援であれば、そのハードルを取り除いたうえで、作業に取り組むことができます。

オフィスへの通勤を「適度な負荷」と感じるか、
それとも「在宅型」の方が自分の本来の能力を発揮できるかを、ひとつの目安にするとよいでしょう。
ちなみに「在宅型」であっても、「完全在宅勤務」(出社なし、フルリモート)で勤められるA型事業所は少なく、
基本的には「月1回~週1回」は通所日で、サービス管理責任者との面談の機会を設けるA型事業所が多い傾向にあります。
② コミュニケーションが直接的か、間接的か

通所型と在宅型の二つ目の違いは、「周囲とのコミュニケーションの取り方」の違いです。
通所型のタイプでは、職員やご利用者同士で、対面で接する場面が多くなります。
業務上で困りごとがあるときは、同じ作業所のオフィス内にいるので、職員に質問がしやすいメリットがあります。
また。お昼休憩などがあるところでは、利用者同士で横のつながりがあったり、作業や仕事についての情報交換ができることも。
一方で、通所型はコミュニケーションが直接的である分、対人関係のトラブルが起きやすいのが難点です。

ひとつのオフィスのなかで、「利用者」「生活支援員・職業指導員」「サービス管理責任者」が毎日顔を合わせることになるので、
性格や意見の不一致、ご利用者の障がいの状況により、事業所内で揉めてしまうケースがよく起こりがちです。
対人関係につまずきやすい方にとっては、作業できる十分なスキルや能力があっても、
事業所内の人間関係に巻き込まれることで、就労が長続きしないケースも見られます。

「在宅型」の就労支援では、就業場所が自宅になり、パソコンを使った「テレワーク」がメインです。
利用者間や職員間で対人トラブルが起こりにくく、適切な距離を保ちながら、自分の作業に集中することができます。
テレワークでは、「電話、メール、Slack(スラック)、Zoom」などのワークツールを使用してお仕事に取り組みます。
対人関係に不安を感じやすい方にとっては、「在宅型」の方が間接的なコミュニケーションになるため、対人不安を和らげながら働くことができます。
人との関わりのなかで成長を実感するタイプの場合は「通所型」、
自宅の落ち着いた環境で作業に集中したい方は「在宅型」に適性があります。
③ チームでの作業か、個人での作業か

「通所型」と「在宅型」の特徴として、日常業務を「チームで作業するか、個人で作業するか」という違いがあります。
A型事業所では、企業が行う業務から障がい者に適した作業を切り出して行うことが一般的です。
通所型の場合は、現地で利用者がお互いに協力しながら進める「軽作業」が多く、
・発送作業
・部品の組み立て
・飲食店での接客
・清掃
・記事作成
・SNS運用
といった種類の作業があります。
通所型では、利用者が一人で作業を進めるケースは珍しく、
慣れるまでは支援員からの指示のもとで、会社内の業務などを補助的に手伝う作業が多くなります。
作業所内のチーム単位で動くことが多いので、利用者同士でも、一定の協調性が求められます。

在宅型は、ノートPCなどを使用した「テレワーク」を行うため、日常的な業務は自宅で一人で進めることになります。
「テレワーク」でも共同で作業を進めることはありますが、
必要なデータの共有や、進め方で分からない点があれば、その都度サポートするという形になります。
人間関係にわずらわされずに作業したい方にとっては、「在宅型」で働くことで、対人ストレスが軽減される面があります。
とくにA型事業所などでの退職理由には「人間関係」を理由にしたものが最も多いと言えます。

これまで「通所型」で人との関わり方に悩まれてきた方にとっては、
在宅型で働くと、自宅が「安心して作業を進められるシェルター」となり、勤務できる期間を延ばしやすいことがあります。
就労に向かう道のひとつのステップとして、「通所型」が合わなければ、「在宅型」に切り替えてみると、新しい働き方が見つかるかもしれません。
その上で、オフィスに通ってチームで協力しながら作業を進めるのが合うのか、
自宅で個人で進めるやり方が合っているのかを、確かめてみるとよいでしょう。
④ テレワークか、軽作業か

A型事業所の作業は、基本的には「軽作業」の仕事内容が多い傾向にあります。
通所型では、事業所のある現地で作業するので、「身体を動かす」お仕事が含まれやすい傾向にあります。
通所型で「身体を動かす」作業は、
・倉庫内でのピッキング
・農作業
・パンやお弁当の製造・販売
・喫茶店のホールスタッフ
・工場のライン業務
などがあります。
身体を動かすことが好きな方にとっては、適性がありますが、一方で、
「腰痛などの持病が悪化してしまう」
「作業ノルマに追い付くことが難しい」
といった、就労の面で課題が見えることがあります。

在宅型の「テレワーク」では、身体的な負担が少なくなります。
在宅の事務作業は、健康状態を維持しやすい、クリーンなお仕事と言えるでしょう。
とくに障がいがあり、病状からの回復過程にある方にとって、負荷の少ない在宅型のテレワーク就労は、トライしやすいお仕事です。
大阪市中央区の就労継続支援A型リライフは、「テレワーク×フィットネス」をコンセプトにしています。
テレワークの職業病とも言える「運動不足」を解消するため、当社のパーソナルトレーナーが、ご利用者に合わせたフィットネスメニューを提供。
運動習慣がない方も、テレワークをしながら、気軽にフィットネスを試すことができる施設となっております。
一般就労に向けて、少しずつ健康を取り戻しながら、自宅で作業することができます。
社用PCの無料貸与やNETFLIXの視聴無料など、充実の利用者待遇でお待ちしております。
通所型と比較した「在宅就労」のメリット
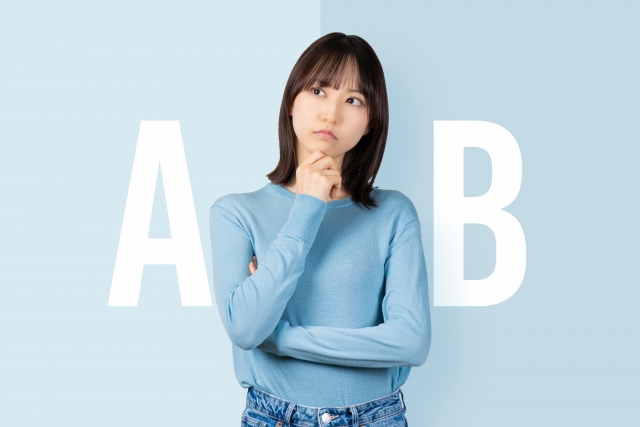
A型事業所の「通所型」には通ったことがあるけれど、「在宅型」は初めての方にとって、
就労することでどのようなメリットがあるか、見えにくい部分もあるかと思います。
通所型と比較したときの「在宅就労」のメリットは。
② 作業後の時間を有効活用できる
③ 人目を気にせずに作業できる
④ 自己管理の習慣が身に付く
⑤ 家族や友人と過ごしやすい
の5つです。
① 朝にゆったりとした時間が取れる

通所から在宅に切り替えたときに、すぐに実感できることは「朝にゆったりとした時間」が取れること。
通勤の支度~出社まで平均して「40~1時間」ほどが掛かるところ、通勤時間がゼロになるため、朝はゆったりと準備ができます。
たとえば、当法人での在宅での出勤方法は、オンラインの勤怠管理システムで打刻し、健康測定の数値を支援員に報告。
支援員から体調確認の連絡を受けたあと、業務がスタートします。
社用PCの起動から10~15分ほどで完了するので、在宅でもスムーズにお仕事ができます。

とくに精神障がいがあり、服薬している薬の副作用でなかなか朝に起きるのが辛い方にとっては、ちょうどいい働き方に感じられると思います。
また朝食を摂ったり、調理の後片付けや、洗濯の時間も取れるため、
通勤がなくなることで、家庭内の生活リズムが整いやすくなります。
起床から朝ごはん、身支度までの時間がしっかりと確保できるので、就労に向けて体調も整っていきます。
② 作業後の時間を有効活用できる

在宅勤務では、自宅を移動せずに作業ができるため、作業後に自由時間が生まれやすくなります。
在宅型のA型事業所で働く場合は、とくに作業後の通勤時間が浮くことを意識して、有効活用してみるのがおすすめです。
たとえば、
・これから就業したい職種の資格勉強に充てる
・興味のある分野の趣味に打ち込んでみる
・次の就業先の求人をチェックしておく
・将来に就きたい仕事のスキル習得・情報収集
などがあります。
これからの就業のための準備期間として、体調を整えたり、
将来に就きたい職業に近づくためのスキルや資格習得の時間に充ててみましょう。

在宅での作業を続けていると、社会的な接点が少なくなりがちなので、
興味のある分野の学びを深める時期として、作業後の時間を捉えると、モチベーションを保ちやすくなります。
就労継続支援A型事業所の制度の主旨は、一般就労に向けての準備的な就労期間となっているので、
少しずつ自分のペースでスキルアップできる場として、A型事業所を活用してみましょう。
③ 人目を気にせずに作業ができる

在宅型のメリットは「人目を気にせずに作業できる」こともポイントです。
通所型の場合、事業所内で職員や利用者同士の人間関係に気疲れしてしまうことがあります。
また、仕事の進め方で意見が食い違ったり、
作業中に話し掛けられることで、目の前の作業に集中できなくなることも考えられます。
在宅勤務では、自宅の環境を整えることができれば、作業に没頭しやすいのが利点です。
とくに障がいの状況により、人とのコミュニケーションに不安を覚えやすい方にとっては、
マニュアル通りに一人で進められる作業が、心理的な安心感に繋がります。
在宅型で作業していて「何かがもの足りない」と感じるときは、そこまでご自身が回復してきた証でもあるので、
その時点で次に通うところを検討してみたり、障がい者雇用などにチャレンジしてみるのもおすすめです。
④ 自己管理の習慣が身に付く

在宅型で働いてみると、通所型に比べて「ひとりでやる」機会が多いことに気が付かれるかと思います。
たとえば、体調が優れない場合、通所型では実際のご利用者の様子を見て、職員がお声がけすることができます。
お互いの顔を見て作業することになるので、支援するスタッフの側でも、ご利用者に異変があれば、気が付きやすいのが通所型の特徴です。
一方で在宅型では、職員がその場には同席しないので、体調が優れないのであれば、自ら申し出る必要があります。

オンラインの勤怠管理(タイムカード)を打刻したり、作業を進めていくスピードや、質問・報告の仕方などは、ご利用者の裁量で任されています。
そのため在宅就労では、自己管理のスキルが自然と身に付きやすい環境と言えるでしょう。
体調や生活リズム、質問・報告・相談の「報連相」などは、通所・在宅の働き方に関わらず、共通の就労スキルです。
ぜひ在宅勤務をはじめる際には、自己管理のスキルを身に付ける練習のつもりで、就労してみるとよいでしょう。
⑤ 家族や友人と過ごしやすい

「在宅勤務」のメリットとして、同居されているご家族やパートナー、友人と過ごしやすくなる特徴があります。
仕事中も自宅やリビングにいる生活となるので、特にお子さんがいらっしゃる育児中の方や、
ご両親の介護が必要な場合も「在宅勤務」が適しているケースがあります。
自宅を離れずに作業ができるので、万が一のときや急な体調不良があった場合も、駆けつけやすく、
家族の様子を見ながら作業ができるので、安心して就労ができます。

また、在宅勤務では身体的な負荷が掛からず、通勤時間もないので、体力や時間の面でも余力を残したまま、週末を過ごすことができます。
在宅勤務では人との繋がりが薄れやすくなってしまうので、
週末は、友人・知人と会う機会を作って話をすると、いい気分転換になります。
「在宅型」で就労するときは、こうしたメリットにも目を向けると、働きやすくなりますよ。