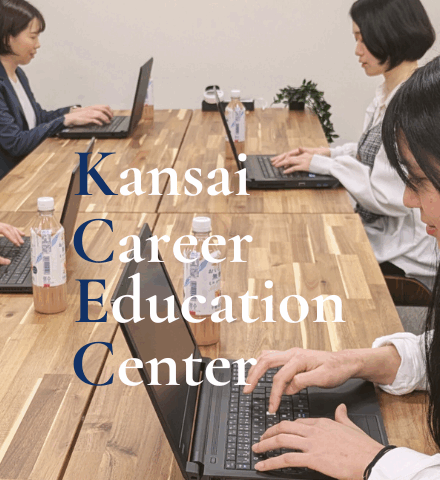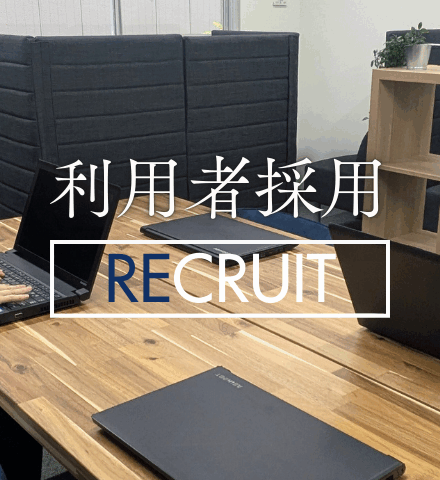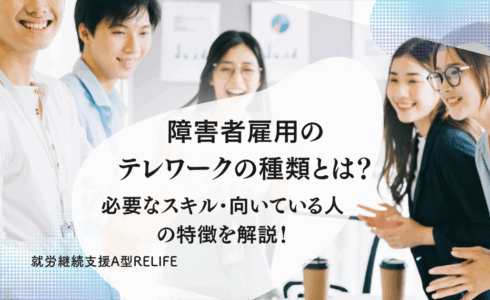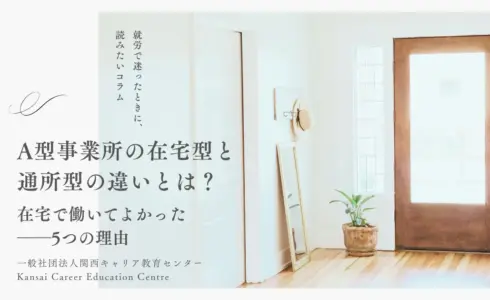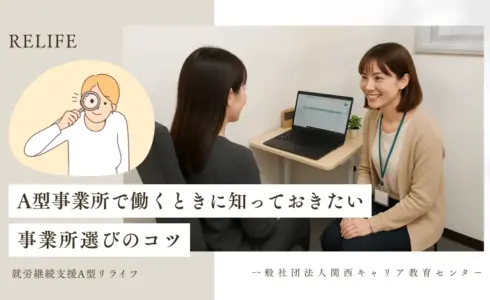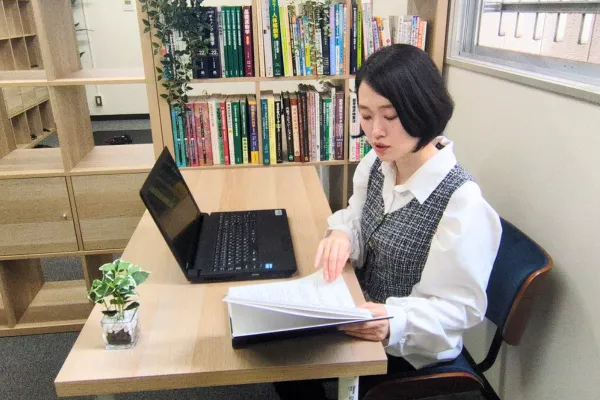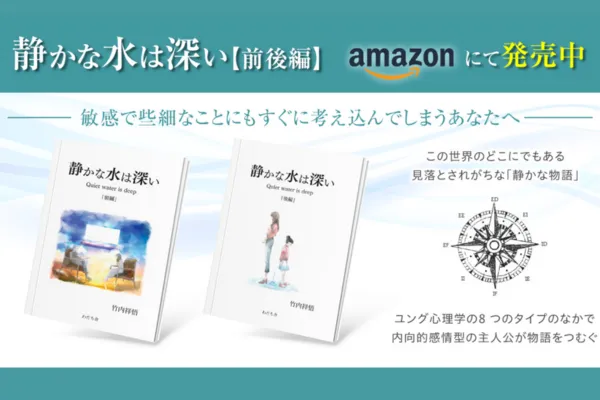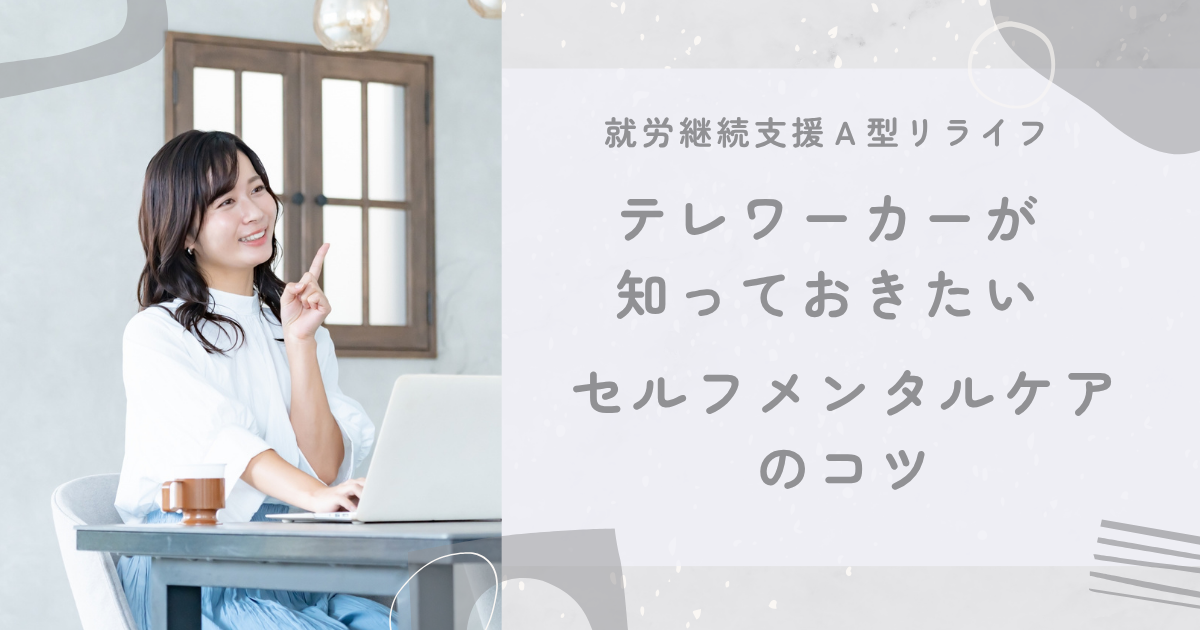
テレワーカーが知っておきたい、セルフメンタルケアのコツ
これからテレワークをはじめる上で、覚えておきたいのが「セルフメンタルケア」です。
テレワークは、出社の必要がなく、インターネットを介した業務が中心で、2020年以降にとくに広まった新しい働き方です。
自宅で就業できるとあって、
「快適に働ける」
「周囲に気を遣わなくていい」
「作業に集中できる」
というメリットを実感する方も少なくありません。
一方で、テレワークの勤務が半年、1年……、とつづいていくと、メンタル面で何らかの不調を感じる方もいらっしゃいます。
今回は、テレワークを長く続けていくための「セルフメンタルケアのコツ」をまとめました。
「テレワーク」をはじめる方や、在宅勤務で悩みがちな方の参考になれば幸いです。
「テレワーク」で気を付けたいメンタル不調のサイン

テレワークの働き方は、合う人にとってはとても快適な働き方になります。
人によっては理想のライフスタイルのように感じられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、「自分ではこの働き方が合っている」と感じていた人でも、のちにメンタル不調のサインが現れることがあるので、
長期でテレワークを続けている方ほど注意が必要です。

テレワーカーのメンタル不調のサインとしては、
② オンとオフの切り替えが難しい
③ 疲れや緊張が取れない
④ 生活リズムが乱れる
⑤ 気分転換ができない
といったものが挙げられます。
では、お悩みごと別に合わせた、それぞれのセルフメンタルケアのコツをチェックしてみましょう。
① 孤立、孤独感を感じる

テレワークでは、主に在宅勤務となるため、平日は人と顔を合わせずに作業するスタイルになります。
対人面でのストレスは抑えられますが、コミュニケーションの機会が少ないことから「孤立、孤独感」に悩む方も少なくありません。
とくに新入社員や若手の社員などでこの傾向は強くあり、
・社内の人間関係ができていない状態でテレワークの生活に入る
・仕事の悩みなどを気軽に相談できる場がない
といった条件が重なると、テレワーカーの「孤立や孤独感」を深めるきっかけになりやすいと言えます。
一方で、中堅社員やベテラン社員でこの傾向が少なくなってくるのは、
・職場以外にも地域に根差した人間関係がある
・社内で気軽に相談や連絡、頼みごとのできる相手がいる
・出社と在宅の割合を自分の裁量で決められる
といった条件の違いによります。

テレワークでよくありがちなのは、こうしたギャップから管理職と従業員のあいだに認識の差が生まれることで、
ベテラン側から見ると、なぜ若手の社員が「孤独感」で潰れてしまうのかが実感として理解できず、
若手の社員側から見ると、その場で相談しても見逃されがちで、ジレンマに陥りやすい構造があります。
会社によっては「まだらテレワーク」の状態(ある社員は出社して、別の社員は在宅になり、出社の割合がまだら模様)になると、
出社している社員と、在宅がメインで作業している従業員のあいだで、コミュニケーションに濃淡の差が出やすいため、注意が必要です。
「孤独感」へのセルフメンタルケア

◎社外の人間関係を大切にする
テレワークが主体の会社では、社員同士のヨコのつながりが薄くなり、社内の人間関係は希薄化する傾向にあります。
業務上での協力関係が中心で、業務外でのコミュニケーションや付き合いが発生しないため、作業のみに集中したい方にとくに向いている環境です。
障害者雇用や就労A型などで、オフィスに通勤・通所されていた方が在宅型の働き方に切り替わると、働き方の違いに驚かれるかもしれません。
とくに人との関わりの中で成長を感じるタイプの方は、このギャップから「孤独感」や「孤立感」を深めやすい傾向があります。

ポイントとしては「社外の人間関係を大切にする」ことで、
以前の職場の友人や、共通の趣味を通じて知り合った知人など、休日に人と会って話す機会を作るのがおすすめです。
実際に人と対面で話すと、とくに何気ない会話でも、
自分のなかのわだかまりが取れやすくなったり、緊張などが和らぐことがあります。
家族関係が良好な場合は、家の手伝いなどをしながら、家族と話す時間を取ってみるのもよいでしょう。
障がいに理解のある場を必要とする場合は、病院や地域のデイケアサービスや、
当事者団体などが主宰する自助グループを探す方法があります。
◎自分の考えや好きなことについて発信する

対人関係が苦手な場合は、ブログやSNSなどを通じて、
匿名で自分の考えていることや悩んでいることを発信してみるのもひとつの方法です。
障がいを抱える方にとって「人と会う」ことは、楽しさを感じることもある一方で、
無意識に他人と自分を比べてしまって負い目を感じたり、慣れない経験から消耗してしまうこともあるかもしれません。
そういうときは、自分にとって安全と感じられる場所で、好きなことについて発信し続けていると、
反応があったり、コメントのやり取りなど、小さな繋がりを作ることができます。
◎人間関係を割り切って考える

テレワークで人とのつながりが薄れやすいのは、業態上、どうしても避けることができないため、
人間関係については、割り切って考えてみることも時には必要です。
テレワークで「孤立」や「孤独感」を感じても、無理にそれを埋めようとして消えるものではないので、
なるべく平常通りにスケジュールをこなしていくこと、目の前のタスクに集中することをおすすめします。
ひととのつながりを望んでも、相手は「そう思わない」「望まない」ケースもあり、
寂しさからひとと繋がろうとするのではなく、
一人でいることを受け入れて、淡々と日常を過ごせるようになることも、社会生活を送っていく上では重要なことです。
② オンとオフの切り替えが難しい

在宅勤務では「オンとオフ」の切り替えが難しいとよく言われます。
オフィスへ出社する方は、
「出勤時刻に合わせて起床」→「服装や身だしなみを整えて通勤」→「オフィスへ入室し、挨拶する」
という一連の流れがあり、この過程で徐々に仕事モードに入っていく方が多いと思います。
また物理的にも「住居」と「職場」が分かれていることから、自然と気持ちの切り替えが起こりやすい仕組みになっています。
一方で、在宅勤務は、生活空間と作業スペースが同じであることが多いため、
意識的なルーティンを作らなければ、オン・オフの切り替えが難しくなります。
オンとオフの切り替え方

◎毎朝、カーテンと窓を開けて換気する
テレワーカーの習慣としておすすめしたいのは、「毎朝、カーテンと窓を開けてみる」ことです。
オフィス勤務の方は、通勤時に日光を浴びる機会があります。
テレワーカーは日光を浴びる時間が少なくなりがちなので、自宅のカーテンと窓を開ける習慣を作ってみましょう。
朝のうちに陽を浴びておくことで、体内時計がリセットされ、目覚めがよくなります。
また、日光を浴びることによって体内にセロトニンが産生されます。
セロトニンは気分を落ち着かせる効果があり、睡眠を司るメラトニンの原料になります。
その結果、寝つきがよくなって睡眠の質が向上し、生活リズムが整う好循環が生まれます。
メンタル面で不調を感じている方にとって「睡眠」がきちんと取れると、快方に向かいやすくなるので、ぜひ試してみてください。

換気も重要な視点で、室内の二酸化炭素濃度の高まりを抑える効果があります。
一般に、室内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えると、テレワーカーの作業パフォーマンスや効率が落ちていく、という研究結果があります。
これは室内の二酸化炭素濃度が上昇することで、作業者が酸素不足に陥り、眠気・倦怠感・頭痛などを引き起こすためです。
とくに夏場や冬場など、エアコンを付けたまま、窓を閉め切って作業する方も多いかもしれません。
テレワーカーがワンルームの部屋(6畳)で作業している場合、窓を閉め切った状態だと30分~1時間以内に1000ppmに到達します。
作業の集中力が切れやすいと感じている方は、休憩に合わせて窓を開け、30~45分ごとに換気を実施してみてくださいね。
◎仕事用の服装に着替える
テレワークでは自宅で作業を行い、周囲の目がない中での作業となります。
そのため、「服装については何でもいい」と思われがちですが、寝間着姿のままで作業するのはNGです。
通勤の際に「服装や身だしなみ」を整えるのは、周囲に不快感を与えないためという意味もありますが、
仕事用の服を着ることによって、着る人自身が「これから仕事へ行く」という気持ちの切り替えに役立っている面があります。

テレワークでも、少なくとも起床後には着替えるようにして、
出社時と同じように、いつでも外出できる姿に整えておきましょう。
なるべく出社するときと同じ習慣を保つことで、スムーズに作業に入ることができます。
ご自身でお気に入りの「ワードローブ」や「仕事用の服」を決めておくと、
テレワークでもモチベーションをアップしながら作業できますよ。
◎お気に入りのルーティンを作る

在宅勤務では、仕事への意識の切り替えが起こりにくいため、
お気に入りのモーニング・ルーティン(朝の習慣)を挟んでみることをおすすめします。
たとえば、
・机周りや足下の床を掃除
・作業前に5~10分ほど読書
・手帳やメモに1日のスケジュールを書き込む
・PCやWi-Fiなど、仕事用のデバイスを充電
といった方法があります。
大阪市中央区の就労A型リライフでは、
健康測定器具(血圧計・体温計・パルスオキシメーター)をご利用者の方に無料で貸与しています。
毎朝の健康測定と記録も、朝の習慣に組み込んでみてくださいね。
普段の「自炊、洗濯、掃除」など、日常生活の用事を済ませていく一連の動作も、仕事モードへ意識を切り替えるポイントになります。
通勤時間が浮いた分は、家事の時間に充てて、生活周りをスッキリさせてみましょう。
家の心配ごとがなくなれば、自然と目の前の作業にも集中しやすくなりますよ。
③ 疲れや緊張が取れない

テレワーカーのあいだで「疲れや緊張が取れにくい」という話もよく耳にします。
仕事とプライベートの境界がうまく作れず、業務が終わったあとも「仕事モード」の緊張が解けていないことが原因のひとつにあります。
疲れや緊張を取るには「オンからオフ」にうまく切り替える習慣がポイントになります。
週のはじめは集中できても、週の後半になると疲れやすい方は、
作業後のリラックス方法を工夫してみましょう。
◎残業はせず、作業後は社用PCを片付ける

当たり前のこと、と思われるかもしれませんが、
終業時刻になったら、その時点で社用PCをシャットダウンし、収納用の鞄やスペースなどに保管しておきましょう。
作業が途中なのでもう少し取り組みたい、という場合もあるかもしれません。
しかし、翌日に疲れを残さないためにも、時間内できっちり作業を切り上げます。
ご利用者のテレワークの作業は、1日で片付くものではなく、長いスパンで繰り返し行っていきます。
途中までの作業になっても、翌日から続きに取り組めるのでご安心ください。
パソコンを机の上から片付けるのは、視覚的にも「仕事の時間ではない」ことを認識させるためで、
作業後の時間に、仕事のことを考えないためのテクニックになります。
パソコンの画面はブルーライトなどを浴びる原因になり、長時間では目が疲れやすくなるので、
目と心を休ませるためにも、終業後はすぐにノートPCを畳み、デジタルデトックスの時間を作りましょう。
◎作業後に1日1回以上、外出する
テレワーカーによくある悩みとして「自室で過ごす時間が長くなる」点があります。
作業後は、意識的に外出の機会を作るのがおすすめです、
自室で過ごし続けると、外界からの接触が遮断された状態になり、
運動不足になるだけでなく、精神衛生上も息苦しさを覚えやすくなります。
テレワーカーにとって外出の機会は、多ければ多いほどよい、といっても過言ではありません。

たとえば、
「図書館や公園までお散歩してゆっくり過ごす」
「スーパーやコンビニへ買い出しに出かける」
「書店やショッピングモールに寄り道する」
など、ご自身にとって外出しやすい理由を作り、気軽にお出かけしてみましょう。
自然のある場所での散歩やジョギングもおすすめで、普段はデジタルなものに触れる時間が多いからこそ、
緑のある遊歩道や公園、河川敷などで、アナログなウォーキングを楽しんでみてください。

歩くことでアイデアが浮かびやすくなったり、
自分自身に意識が向いて悩みがちなことを、一旦、外に逃がすことができます。
外に出てリフレッシュしたあとは、ご自身で深めたい分野やスキルの習得などに時間を充ててみましょう。
運動したあとの時間は集中しやすい状態になるので、自己学習にもおすすめです。
仕事以外のところにもう一つの軸ができると、興味が広がって外に出やすくなる好循環につながります。
◎運動する習慣を作る

テレワーカーの仕事でも、身体が資本であることに変わりはないので、運動する習慣をつくっておくのがおすすめです。
テレワークでは、椅子の座りすぎや、姿勢が固定されることにより、
「肩こり・腰痛・骨盤のゆがみ」などが出やすく、テレワーカーの職業病とも言われます。
こうした症状は、ストレッチやジョギング、ジムトレーニングなどで改善することができます。
在宅の仕事を長く続けていきたいと考える場合は、「テレワークと運動」はセットで考えるようにしてみましょう。
就労継続支援A型リライフでは、パーソナルトレーナーによるフィットネスの機会を無料で提供しております。
運動がはじめての方も取り組みやすいメニューをご用意しており、トレーナーと一緒に気軽に運動習慣を作ることができます。
テレワークで悩みがちな症状に効くストレッチや、やさしい筋トレなどをフィットネスで行います。
ぜひリライフで「テレワーク×フィットネス」の生活をスタートしてみてくださいね。
④ 生活リズムが乱れる

自宅で就業すると、周囲の目が入りにくい分、生活リズムは乱れやすくなる傾向があります。
一旦、リズムが崩れてしまうと、体調や症状を悪化させる原因にもなり、
勤怠が安定せずに月の収入が少なくなったり、会社にも迷惑を掛けてしまうことになりかねません。
リライフで就業する場合は、平日の週5日の出勤が求められるため、
生活リズムを安定させることが、就労の第一歩につながります。
生活リズムの整え方のコツ
◎起床と就寝の時刻を揃える

生活リズムを整える上で、最も重要なことは「起床と就寝の時刻」を揃えることです。
メンタル面での症状の原因を辿ると、「眠れていないこと」がひとつの要因になっていることがあります。
メンタルクリニックや精神科などでも「決まった時間に起きて、決まった時間に眠る」ことは、医師から推奨される方法でもあります。
入院などの際に、起床・消灯の時刻や食事の時間が決まっているのは、
院内での生活リズムを一定に保つためであり、この考え方は在宅での働き方にも有効です。
22~23時までに消灯する、というマイルールを作り、布団にきちんと入る習慣を付けましょう。
眠れない場合でも、目を瞑って何もせずに身体を横たえているだけで、回復の効果はあります。
スマートフォンやタブレットなど、0時を超えても使用してしまう場合は、デジタルデバイスへの依存状態になっています。
消灯時刻になれば、スマートフォンは引き出しや収納の奥にしまい、布団から手の届かない位置に置くように工夫しましょう。
◎朝食を摂る

生活リズムを整える点で、朝食を摂ることもおすすめの方法のひとつです。
テレワークでは運動量が少なくて済むため、朝食もつい抜いてしまいがちですが、
生活リズムを司っている体内時計をリセットするためには「朝食を摂る」ことが重要とされています。
時間栄養学、という考え方があり、たとえば、同じパンやソーセージ、卵の食事であっても、
食べる時間によって栄養が効果的になる時間帯があり、代謝にも変化が現れます。
たとえば、朝の時間のうちは炭水化物(ごはん・パンなど)も消費しやすいので、
朝食で食べると太りにくくなり、体内時計の活性化にも繋がります。
近年ではファスティング(絶食時間を作る)ダイエットも流行していますが、
抜くのであれば朝食よりも夕食の方がより効果的であるため、
朝と昼はとくにしっかりと食事を摂るように心がけましょう。
⑤ 気分転換ができない

中長期にわたってテレワークを続ける方にありがちな悩みは「気分転換ができない」ことです。
とくに在宅の事務作業では、作業環境や内容に変化が乏しく、毎日の作業が単調な繰り返しに感じられることもあるでしょう。
そのため、作業に慣れている方ほど、マンネリ化への注意が必要で、
自分なりの「気分転換のコツや方法」を持っておくことが大切になります。
◎こまめに休憩すること
テレワーカーの気分転換のコツとして「こまめに休憩を挟むこと」が挙げられます。
オフィスで働いていたときは、お昼休みの時間が決まっていたり、作業の手を少し止めて同僚と話し合う時間があったりしますよね。
在宅勤務では、職員がその場にいないため、ご利用者の方に「休憩です」とお声がけすることはできません。
そのため、ご自身で意識的に休憩を取りに行く必要があります。

とくにパソコンに向かう作業は、人によっては過集中の状態になりやすく、
作業中に一度も休憩を取っていない方は、1時間に1回は、手を休めてみてくださいね。
休憩を取るおすすめの方法は、「椅子から立ち上がる」ことで、
・部屋の窓を開けに行き、換気をする
・間食(チョコレートやナッツなど)を小皿に盛る
・その場でストレッチや伸びをしてみる
・深呼吸をする
など、少し動作を加えた休憩の取り方をすると効果的です。
5分~10分程度、目の前の作業から離れる時間を作ることで、
気持ちをリセットしながら、作業を続けていくことができます。
◎作業後に趣味の時間を楽しんでみる

業務で行えるPC作業の範囲は限られているため、同じ作業の繰り返しに感じられる方は、
作業後の時間の過ごし方を工夫してみましょう。
大阪市中央区の就労継続支援A型リライフでは、ご利用者の作業時間は1日2時間となります。
余暇の自由時間が多く取れることがポイントで、
「作業のほかに自身で打ち込みたいことがある」方にとくにおすすめする事業所です。
A型事業所は、社会に復帰する一歩手前のステップで、病気や症状とうまく付き合いながら、
ご利用者が働くための方法を模索できる場所でもあります。

リライフでは、業務の負荷を最小限にし、プライベートの趣味の時間もたっぷりとれるので、
「楽しみながら働くこと」を体験しやすいA型事業所と言えます。
目指したい職業があり、目的を持って資格勉強をされる方には、
参考書やテキストの購入補助や、社内蔵書の貸出なども行っております。
この機会にぜひ、大阪市中央区の就労A型リライフをご利用くださいませ。